かつてドイツには 徴兵制度(Wehrpflicht) がありました。
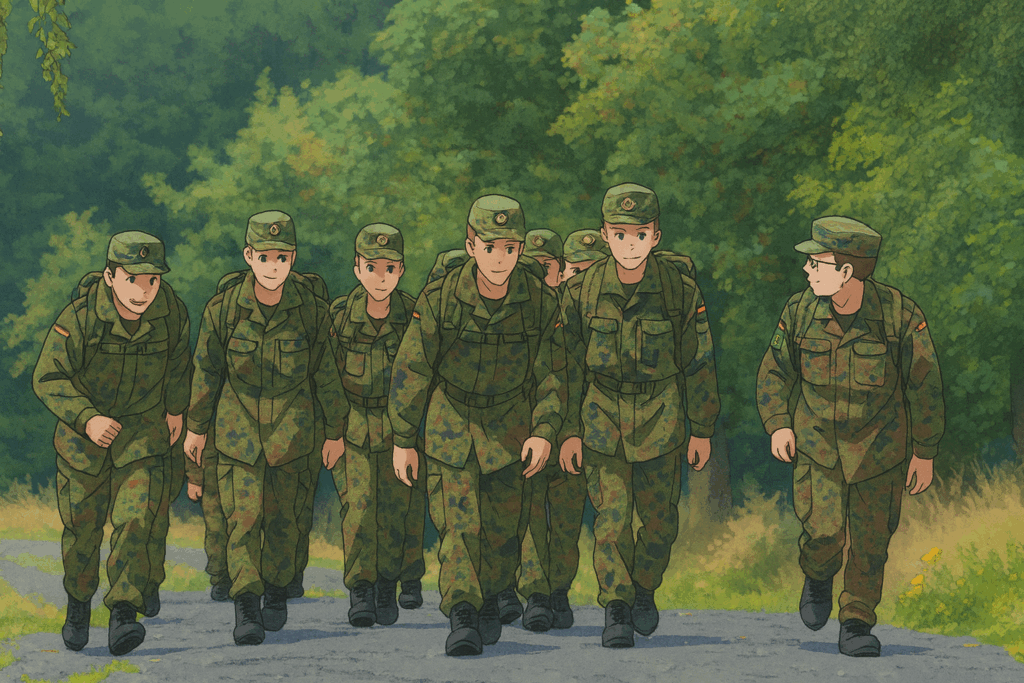
徴兵制度 イメージ図
対象者は、ドイツ国籍を持つ男性のみが対象 で、外国人には義務はありませんでした。
【制度が始まった背景】
・第二次世界大戦後の西ドイツ(旧・連邦共和国) では、冷戦下の安全保障上の理由から1956年に徴兵制が復活しました。
・ただし、ナチス時代の強制的な兵役の経験が国民に深く残っていたため、「兵役拒否の自由」 が憲法(基本法)で認められました。
・その結果、「戦争は嫌だが、国家や社会に貢献はする」という選択肢として Zivildienst(社会奉仕) が用意されたのです。
【社会奉仕(Zivildienst)の実態】
・配属先は、主に 病院、老人ホーム、介護施設、障がい者支援施設、救急サービス など。
・「おむつ替えをしていた」「救急車の助手をしていた」「介護施設で食事介助をしていた」といった体験談が多くあります。
・若い男性が全国各地の社会施設に派遣されたため、福祉現場に欠かせない労働力 となっていました。
【ドイツ社会への影響】
(1)福祉への人材供給
・Zivildienstは「安価な労働力」として機能し、福祉施設にとってはなくてはならない存在でした。
・制度が廃止された2011年以降、現場の人手不足が深刻化 したと報告されています。
(2)若者の社会経験
・多くの男性が 若いうちに介護や障がい者支援の現場を経験 するため、社会的な視野が広がり、ボランティア精神や社会的責任感を育てる効果がありました。
・一部の人は、この経験をきっかけに医療・福祉系の進路を選ぶようになったと言われています。
(3)ジェンダー面の議論
・義務は「男性のみ」であったため、男女平等の観点から批判 もありました。
・制度廃止後は、男女ともに参加できる Freiwilligendienst(任意奉仕活動) が導入され、男女平等の形になっています。
【制度廃止とその後】
・2011年にメルケル政権が徴兵制を「停止」し、事実上廃止。
・同時に、Bundesfreiwilligendienst(連邦奉仕活動制度) が発足し、若者やシニア世代までもが任意で社会奉仕に参加できる仕組みになりました。
・現在は、ボランティア精神を育む教育的制度として位置づけられています。
【兵役(Wehrdienst)を選んだ人の体験】
生活・訓練
・期間:おおよそ 9か月〜1年(時期によって変動)
・場所:国内の軍事基地(Bundeswehr)
・内容:基礎訓練(射撃、行進、体力訓練など)+その後の配置(通信、後方支援、戦車部隊など)
・生活:兵舎での共同生活。規律が厳しく、上下関係や時間管理を徹底的に学ぶ場だった。
メリット
・給与(手当)がZivildienstより高め。
・軍事技術や規律を学べる → 後のキャリア(警察、消防、治安関係)に役立つ。
・国防に直接関わる「誇り」を持つ人も多かった。
デメリット
・身体的に厳しい。
・軍事訓練や武器使用に抵抗を感じる人も少なくなかった。
・当時は「兵役は時代遅れ」と感じる若者も増えており、モチベーションが低い人もいた。
【社会奉仕(Zivildienst)を選んだ人の体験】
生活・活動
・期間:兵役と同程度(9か月〜1年)
・場所:病院、老人ホーム、救急車、障がい者施設など
・内容:介護(入浴・食事介助)、清掃、車いすの補助、救急搬送の助手など。
・生活:施設勤務のため、通常の自宅生活をしながら通勤するケースが多かった。
メリット
・人との触れ合いが多く、人生観が広がる。
・介護・医療の進路を考えるきっかけになる。
・武器を持たずに「社会に貢献している」という誇り。
デメリット
・体力的にきつい介護作業も多かった。
・給与(手当)は兵役より安い。
・「兵役を逃げた」という偏見を持つ人に出会うこともあった。
【まとめ】
・兵役は「規律と国防の経験」、Zivildienstは「福祉と社会貢献の経験」。
・経験の質はまったく異なりますが、どちらも当時の若者にとって「社会に出る前の通過儀礼」のような意味合いを持っていました。
*車椅子 軽量【Care-Tec Japan/ケアテックジャパン】おしゃれ介護福祉用具*

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ba68940.65dceb12.4ba68942.1c583c21/?me_id=1306882&item_id=10001869&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhukusi-orosi%2Fcabinet%2Fw31%2Fsum%2Fn001-sum.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


