ドイツの教育システムは「早い段階で進路を決める」という点が特徴的です。
子どもは比較的若いうちに「学問(大学進学)」の道か「職業訓練(職人や専門職)」の道に進むかを振り分けられる仕組みになっています。
【小学校まで(Grundschule)】
小学校は通常 1年生から4年生(6歳~10歳ごろ)。
この時点で 担任や学校と家庭の話し合いを通して、次にどのタイプの中等教育へ進むかを決定します。
【中等教育(5年生以降)の進路】
小学校を終えた後、以下のような学校に分かれます:
- Gymnasium(ギムナジウム)
・大学進学を目指す子ども向け。
・12~13年生まで学び、最終的に「アビトゥーア(大学入学資格試験)」を取得します。
- Realschule(レアルシューレ)
・実務的な職業や専門学校への進学を目指す。
・卒業後は職業訓練や上級学校(Fachoberschuleなど)に進むことも可能。
- Hauptschule(ハウプトシューレ)
・主に手工業や職人系の職業訓練(デュアルシステム)に直結。
・15~16歳で卒業し、その後は企業で働きながら職業学校に通います。
実際に「職人の道」を選ぶ時期
・具体的に 職業訓練(Ausbildung)に進むのは15~16歳ごろ。
・ただし、方向性そのものは **小学校卒業(10歳前後)**の時点で「大学進学を見据えるか」「職業系に進むか」が大枠として決まってしまう、というのがドイツの特徴です。
【補足】
・ただし州によって制度の柔軟性は異なり、途中で進路を変更できる仕組みもあります。
・近年は「総合学校(Gesamtschule)」が増え、進路変更の余地が広がっていますが、基本的に早期選択の伝統は残っています。
【まとめ】
・**10歳ごろ(小学校卒業時)**にまず進路の方向性を決め、
・15~16歳で実際に「職人としての職業訓練」か「さらに学業を続けるか」を決断する、という流れです。
【日本との違い】
メリット・デメリット比較表
| 視点 | ドイツのメリット | ドイツのデメリット | 日本との違い |
| 進路決定の早さ | 子どもの適性を早く見極められる。 | 10歳での判断は早すぎる場合もあり、後で後悔する人も。 | 日本は高校卒業(18歳)まで進学か就職かを決める余裕がある。 |
| 職業教育 | デュアルシステムで実践的に学べる。卒業後すぐに即戦力として働ける。 | 一度職業訓練に入ると大学進学の道が狭まることも。 | 日本は「大学進学 or 就職」の二択で、職業訓練の選択肢が少ない。 |
| 社会的評価 | 職人や技術職も高く評価され、収入も安定しやすい。 | 学歴社会的な評価は依然として強く、ギムナジウム進学が「エリート」と見られる傾向も。 | 日本では大学進学が「成功コース」とみなされがち。職人や専門職はまだ低めに見られることも。 |
| 柔軟性 | 州によっては進路変更が可能で、Realschuleから大学進学に進む道もある。 | 学校の仕組みによっては進路のやり直しが難しい。 | 日本では浪人や専門学校など、比較的やり直しの選択肢が多い。 |
| 社会との接続 | 16歳から社会人として働きながら学ぶ経験が積める。 | 若いうちに「大人の責任」を負わされるため、精神的に負担になる場合も。 | 日本は大学卒業(22歳)まで「学生」でいられる猶予が長い。 |
まとめ
・ドイツでは 「早期決断」+「職業教育の充実」 が特徴。
・日本は 「進路決定が遅い」+「大学進学偏重」 が特徴。
・どちらにもメリットとデメリットがあり、特にドイツでは「職人=立派なキャリア」と認められている点が大きな違いです。
*万年筆 モンブラン 145 マイスターステュック クラシック MONTBLANC ブラック*
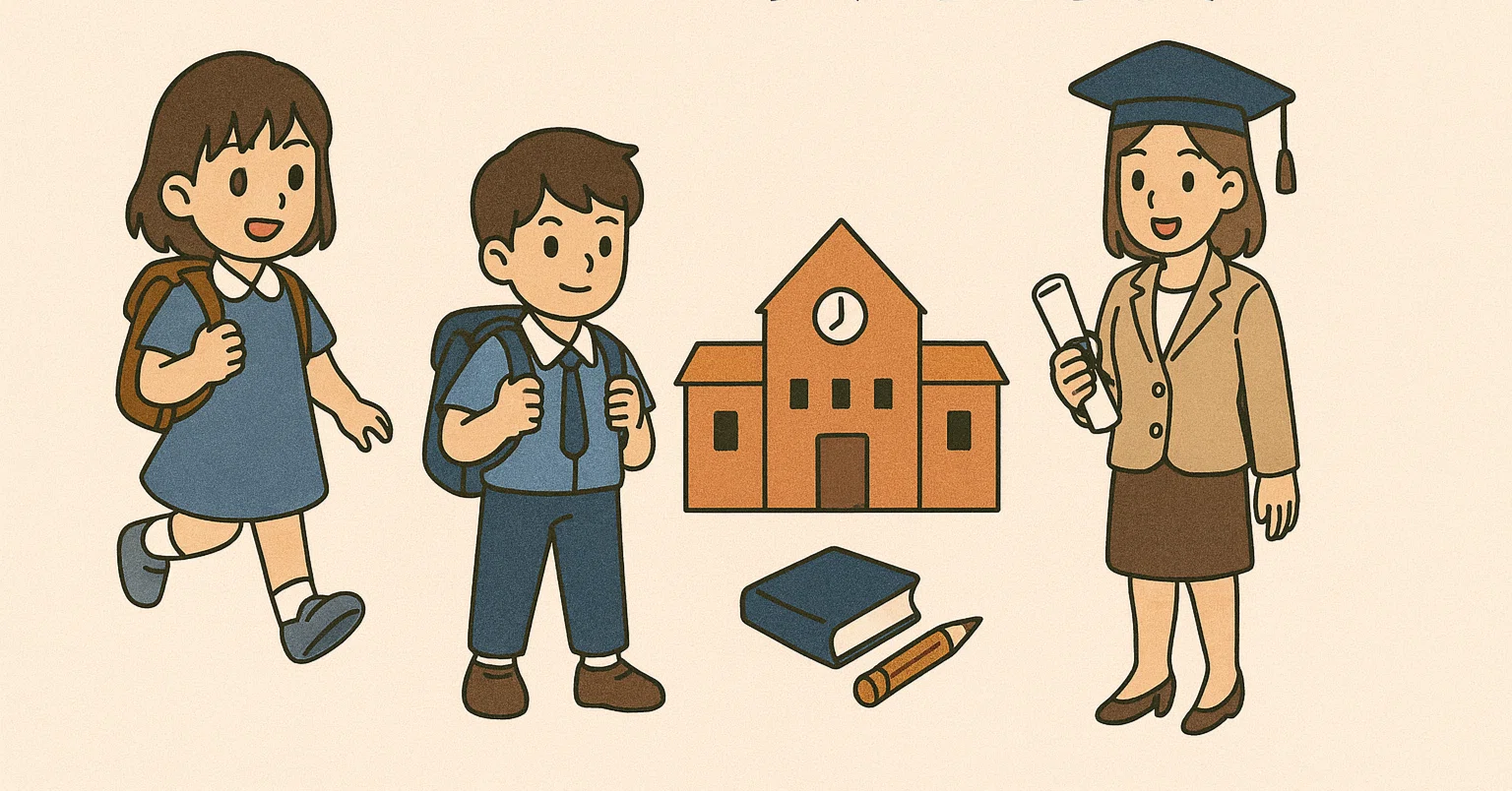
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bb68d28.fb6d8225.4bb68d29.cfdbcac2/?me_id=1241849&item_id=10032864&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-youstyle%2Fcabinet%2Fmontblanc%2Fmb145-800_08.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


