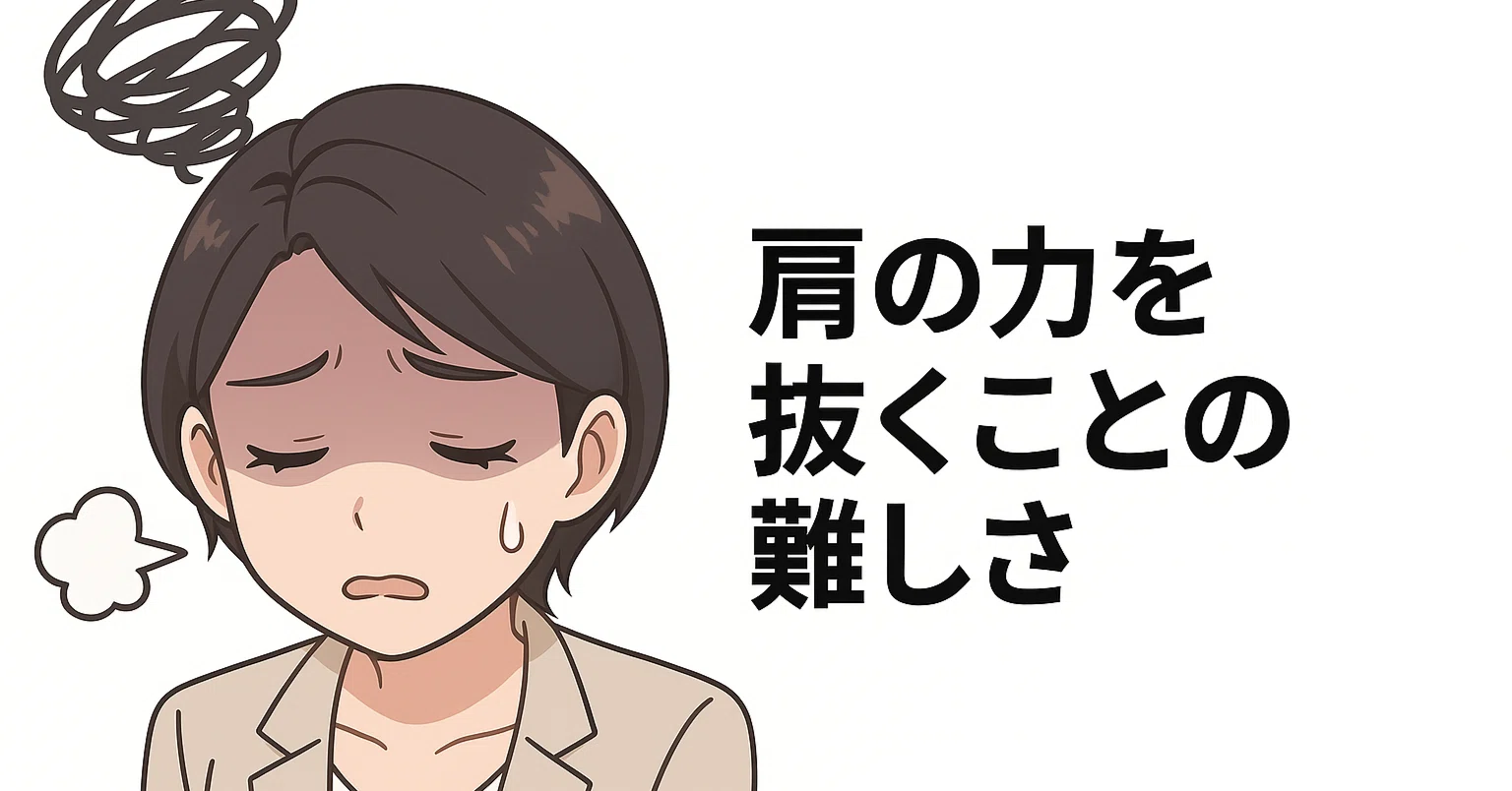剣道の練習でも仕事でも、よく周りの方達に「もう少し肩の力を抜いた方が良いね。」と何度も言われてきました。
これが、いまだに難しく、自然に「力を抜く」ことができません。
私の場合、「力を抜く」=「手を抜く」=「怠けている」=「悪」という風にとらえてしまいます。
「抜くところは抜かないと、身が持たないよ。」とも言われたこともあります。
例えば、剣道の練習の場合、肩の力を抜くと、お腹の力まで抜けてしまい、なんとなく、気合も入りません。
かといって、力み過ぎると、上半身に力が入りすぎて、心と体がバラバラの感覚に陥ってしまいます。
練習時間が多くなればなるほど、当然、体がきつくなり、無駄な動きがなくなります。
エネルギーが切れて、動けなくなっていしまうという表現が正しいのかもしれません。。。(T-T)
つまり、良い意味で力が抜けて、そのときに打った一本には、冴えがあり、気持ちの良い打ちになることがあります。
試合や審査で放たれる一本は、体力的、また、精神的にしんどい場面で一所懸命に練習したときの打ちがほとんどです。
私は不器用なので、今も一つ一つ練習の中で、肩の「力を抜く」ことを体に覚えこませるようにしています。
一方で、仕事では、これまでどうだったのかを振り返ると、やはり、力み過ぎていたようです。
正直、力の加減ができないことが、コンプレックスでした。
明日へ回せることも、今日、返事をすれば、相手先も喜んでくれるし、安心するだろうと、内容にも一語一句、気を配りました。
特に剣道関係の仕事をしていた際は、やり取りする各国の剣道連盟関係者のほとんどがメインの仕事を持ち、ボランティアで連盟を支えていました。
彼らは、剣道関係の仕事に費やせる時間に限りがありましたので、彼らから連絡が来たら、すぐに対応できる体制を取っていました。
国際剣道連盟には、64ヵ国・地域の剣道連盟がいました。
当然、日本との時差が大きい国もあり、夜、寝る前に連絡が来たりすることもよくありました。
私の性格上、放っておくことが出来なかったものですから、何らかの返信をすることを心掛けていたお陰で、各国の剣道連盟とは良い関係を築くことができました。
剣道がこれだけ海外へ普及されているのも、各国剣道連盟の皆さんが、日頃から一所懸命、練習を続け、そこに楽しみや喜びを見出してくれているお陰だと思っています。
ドイツで大人の初心者やこどもを教えることがあり、指導中、「肩の力を抜いて。」と私自身がよく言っていたことを思い出しました。
人に指導しておきながら、自分がいまだにそれができずに悩んでいます。
当時、指導した生徒の皆さんに顔向けできません。
今からでも遅くないので、「肩の力を抜く」ことを体現し、言葉でしっかり説明できるようになりたいと思います。
皆様が、どのような方法で、「肩の力を抜いている」のか、コメント欄にて教えていただけるとうれしいです。^ ^